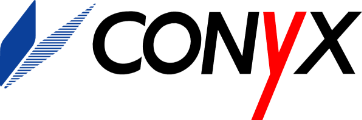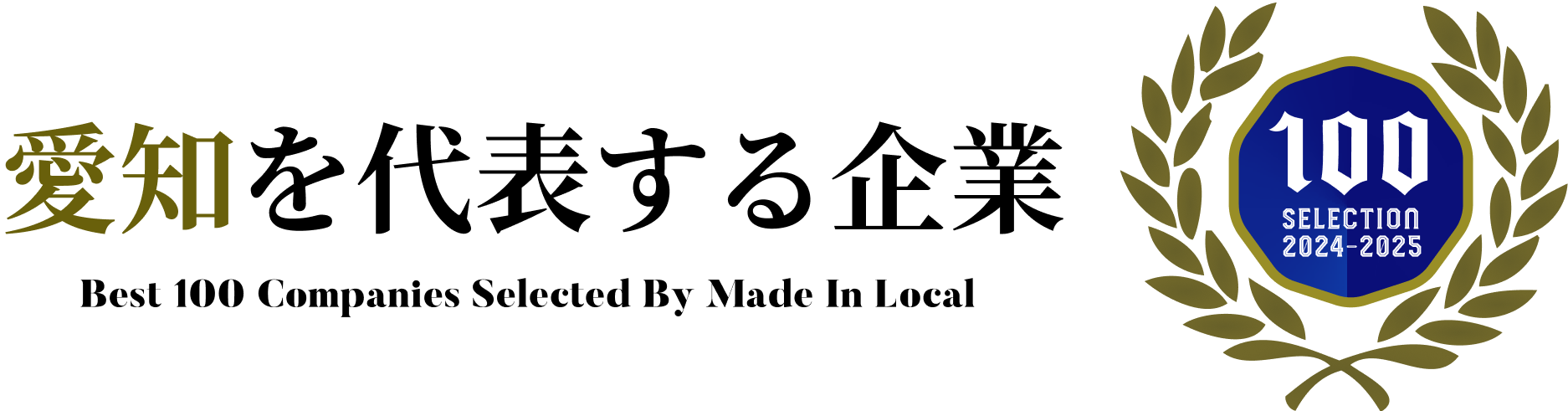点検
ビルのガス設備についてガスの種類や点検など基本的な事柄を解説

ビル管理者の方の中には、ガス設備の導入や維持について詳しく知りたい方もいるのではないでしょうか。この記事では、ビルのガス設備についてまず知っておきたい基本的な事柄を解説します。
ガスの種類
ビルや一般家庭でエネルギー源として使用されるガスは、都市ガスとLPガスの2つに大別されます。
ガスの種類によって、ガスを使うまでに必要な配管やメリット・デメリットが異なるため、それぞれのガスの概要を押さえておくと便利です。
ここからは、都市ガスとLPガスの特徴について解説します。
都市ガス

都市ガスは、メタンを主成分とした天然ガスを冷却し液化した「液化天然ガス」(LNG:Liquefied Natural Gas)を原料としたガスです。
液化天然ガスは工場で貯蔵し、気化した後で、「ガバナ」という設備で圧力を調整しながら道路の地下にある導管を通じてビルや一般家庭などに供給されます。
供給先の建物によって、供給されるガスの圧力は異なります。ガスの圧力と供給先の建物の表は以下の通りです。
| 供給方式 | 供給圧力 | 供給先の建物 |
|---|---|---|
| 低圧 | 0.1MPa未満 | 小規模なビル・一般家庭など |
| 中圧 | 0.1MPa以上1.0MPa未満 | 大規模ビルなど |
| 高圧 | 1.0MPa以上 | 大規模な工場・発電所など |
日本国内で使われている都市ガスは、さらに7グループ13種類に分かれます。主な規格は、「13A」または「12A」です。
都市ガスのメリット・デメリット
都市ガスの主なメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| LPガスより料金が安いことがある ・ガスボンベ置き場が不要 | 災害時などにガスが使えない可能性がある ・サービス提供エリアが限られる |
都市ガスのメリットとしてよく挙げられるのは、LPガスと比較した際の料金の安さです。ガスの利用料金が抑えられれば、月々のランニングコストも抑えやすくなります。
しかし、実際の料金は地域やガスの事業者によって異なります。例えば当社が所在する愛知県でも、複数のガス事業者がさまざまな料金設定でガスを提供しているため、一概にどちらのガスが安いとも言えません。
都市ガスは、都市部などガスの導管が整備されている地域のみで利用でき、ガスボンベ置き場を用意する必要がありません。しかし、災害時などにガスの供給がストップするとガスが使えなくなることには注意が必要です。
都市ガスを使いはじめるには
ガスの引き込みがない建物で新しく都市ガスを使いはじめるには、道路の地下にある都市ガスの導管から敷地内にガス管を引き込む必要があります。
事前に調査や見積もりをするためにも、都市ガス事業者に連絡を取りましょう。ガスの使用開始には、ガス管の引き込みだけでなく、メーターの設置やガス使用箇所への配管が必要です。
工事期間は状況によってまちまちで、道路の掘削などに時間がかかり、1ヵ月以上の期間が必要なケースもあります。
LPガス

LPガスはプロパンやブタンなどを主成分とする「液化石油ガス」(LPG:Liquefied Petroleum Gas)です。圧力を加えて液化させた状態で、ガスボンベに充填されており、常温・常圧になると気化します。
収納庫や軒下などにガスボンベを設置し、使用します。供給にあたりガスの導管が必要で都市部を中心にサービスが提供されている都市ガスと異なり、設備さえ整えれば全国どこでも使えることがLPガスの大きな特徴です。
LPガスのメリット・デメリット
LPガスの主なメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 都市ガスよりも幅広い地域で利用可能 ・災害時などでもガスを使いやすい | 都市ガスより料金が高いことがある ・ガスボンベ置き場が必要 |
LPガスは都市ガスがサービスを提供していない地域でも利用可能です。また、使用するガスを建物付近のガスボンベに貯蔵しているため、災害などがあっても安全面で問題がなければ引き続きボンベ内のガスを使用できます。
デメリットは、都市ガスよりも料金が高いことがあることです。ただし、実際の料金は地域や事業者によっても異なるため、必ずしもLPガスの料金が高いとは限りません。
LPガスは料金の変動がやや多く、料金体系が不透明な事業者もあるため、都市ガスよりも料金の見通しをつけづらい傾向はあります。
また、LPガスを使うためには安全な場所を確保してガスボンベを置く必要があります。
LPガスを使いはじめるには
LPガスの場合は道路の掘削工事などは必要なく、ガスボンベを設置し、建物内でガスが使えるよう配管します。
ガスボンベが設置できる場所は、火気から離れた水はけのよい水平の場所で、周囲の温度を40度以下に保てる所などさまざまな条件があります。
ガス機器の種類
ガスを燃焼させて利用するガス燃焼機器(ガス機器)は、給気・排気の方法によって以下の3種類に分かれます。
| ガス機器の種類 | 概要 |
|---|---|
| 開放式ガス機器 | 室内で給気・排気を行う |
| 半密閉式ガス機器 | 室内で給気し、室外に排気する |
| 密閉式ガス機器 | 室外から給気し、室外に排気する |
開放式ガス機器に関しては、換気が十分に行われない状態で仕様を続けると、屋内の空気が排気によって汚染されます。結果として、ガス機器の不完全燃焼にもつながり、一酸化炭素中毒の原因ともなるため、換気に注意が必要です。
ガス警報器の設置
都市ガスやLPガスを使用しているビル・施設では、ガス警報器(ガス漏れ警報器)の設置が義務づけられている建物があります。
対象となる建物は、地下街や超高層建物、不特定多数の人が利用する施設などで、都市ガスとLPガスのどちらを使っているかによっても設置義務があるかどうかが異なります。
詳しくは、ガス警報器工業会の下記の資料などをご参照ください。
ガス警報器は、ガスの種類によって以下の場所に設置します。
| ガス警報器の種類 | 設置場所 |
|---|---|
| 都市ガスのガス警報器 | ガス機器から水平距離8m以内で天井面から30cm以内の位置 |
| LPガスのガス警報器 | ガス機器から水平距離4m以内で床面から30cm以内の位置 |
都市ガスの警報器では天井近くに設置し、LPガスの警報器で床近くに設置するのは、ガスの空気に対する比重が異なるからです。
都市ガスは空気よりも軽いため上方に移動し、LPガスは空気よりも重いため下方に移動します。
ガス設備の点検
ガス設備を安全に使い続けるためには、定期的な点検が必要です。ここからはガス設備の主な点検について解説します。
法定点検
ガス設備には法定点検が定められています。法定点検には、ガス導管事業者が行う「内管漏洩検査」とガス小売事業者が行う「ガス消費機器調査」があります。
点検頻度は4年に1回以上です。事業者によっては利用者の状況に応じて2年に1回以上の頻度で点検を行うこともあります。点検の結果、ガス機器の修理や交換が必要になった場合は別途費用が必要ですが、点検のみであれば費用はかかりません。
どちらも点検の責務があるのはガス事業者側ですが、ガスを安全に使い続けるために利用者側も点検に協力する必要があります。
その他の点検
ガス事業者やガス機器のメーカーが、標準使用期間を迎えるガス機器を主な対象として有料で任意の点検を提供している場合があります。
基本的には標準使用期間を迎えるタイミングで点検をすすめられることが多いですが、ガス機器を使用している期間であれば、いつでも点検の申し込みができます。
ガス機器の使用状況によっては、標準使用期間より短い期間に劣化が進むこともありえるため、不具合や異状に気付いた場合は点検を申し込みましょう。
当社の強み・メリット
総合ビルメンテナンス企業である当社は、今回ご紹介したガス設備にも携わっており、様々なビルにまつわるメンテナンス業務を一手に引き受けることができます。その他、当社には以下のような強みがありますので、ビルメンテナンスに関して何かご相談がありましたら、コニックスに是非ご相談ください。
コニックスへの問い合わせ
- 総合ビルメンテナンス企業として、建物にまつわる悩みごとはトータルでご相談をお受けすることができ、解決が可能です。
- 施設管理のベストパートナーであり続けられるよう、変化を恐れずチャレンジする文化(マインド)が根付いているため、より良いサービスを提供することができます。
- 創業(1955年)以来、長きに渡り培ってきた圧倒的な経験値(ノウハウ・スキル)を持ち、多種多様な顧客や施設利用者様から高い評価を得ています。
- エコチューニング事業所認定・エコチューニング技術者がいるため、省エネ知識も豊富で、水道光熱費といったランニングコストの軽減にも貢献できます。
- 特に愛知県においては拠点数が多く、何かあったときにすぐに駆け付けるといった充実した支援体制が整っています。