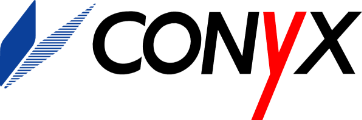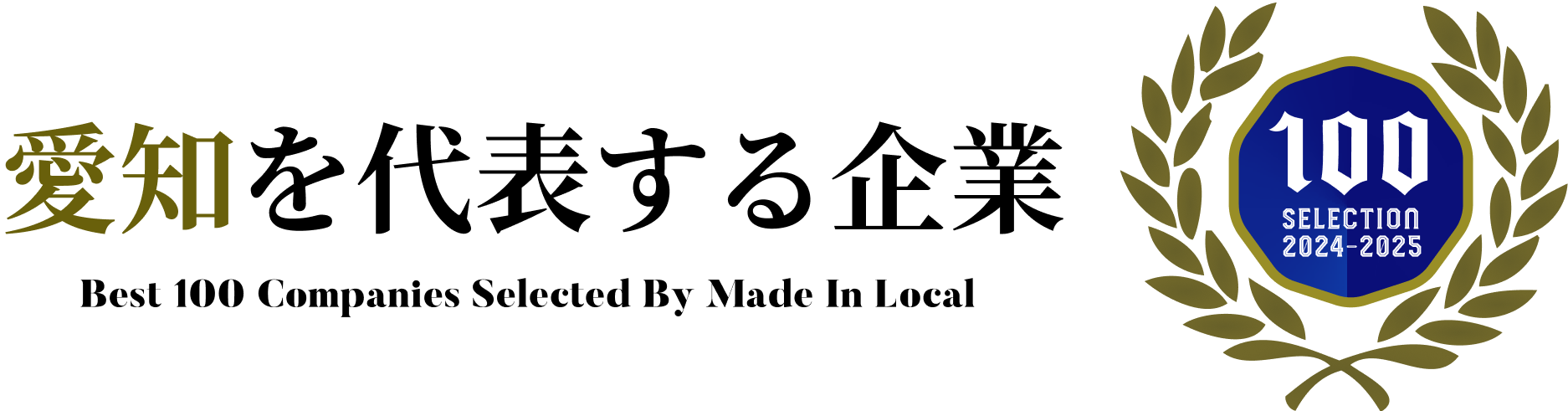点検
ビルの給湯設備について給湯方式や検査・清掃の概要を解説

ビルの給湯設備は、温水を安全かつ快適に提供するために定期的な検査・清掃が必要です。しかし、そもそも給湯設備がどのような機器で成り立っており、どのような検査・清掃が必要か把握していない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、給湯設備の概要や給湯方式など基本的な情報をまず解説し、給湯設備に必要な検査・清掃を紹介します。
給湯設備とは

給湯設備とは、建物に温水を供給するための設備です。ビルの給湯設備には例えば以下の機器が含まれます。
- 温水ボイラ
- 貯湯タンク
- 熱交換器
- 循環ポンプ
- 配管
- 給湯栓
給湯設備は、建物の規模や給湯箇所、必要な給湯量などに応じて設計されており、建物によって給湯設備を構成する機器や給湯方式が異なります。例えば、温水をためておく貯湯タンクがない給湯システムや循環ポンプを使わない給湯システムもありえます。
また、配管の仕方や、温水の循環方式・加熱方式もさまざまです。一般の方が給湯設備の細かな部分まで把握するのは大変ですが、管理しているビルの給湯設備がおおむねどのように成り立っているか把握すると、メンテナンスの見通しもつけやすくなります。
給湯方式
給湯設備の検査・清掃について分かりやすく説明するため、給湯設備の基本知識のうち、「給湯方式」のみ簡単に解説します。給湯方式には、「中央式」と「局所式」があり、建物によってどちらか一方のみ使う場合もあれば、併用する場合もあります。
中央式の給湯設備では水質検査の規定があるため、管理しているビルの給湯方式が中央式かどうかだけでも確認しておきましょう。ここからは、それぞれの給湯方式について解説します。
中央式
中央式とは、機械室など特定の場所に貯湯タンクや温水ボイラを設け、建物の複数箇所に温水を供給する給湯方式です。
中央式はホテルや病院など、大量の温水を必要とし、給湯箇所が多い建物で採用されます。大量の温水を効率的に供給しやすい一方で、配管や設計は複雑です。
中央式では複数箇所に温水を供給する都合から配管が長く、多くの場合配管での湯温低下に対処するため「返湯管」という管を設けて温水を循環させる必要があります。
また、中央式は温水の汚染がより懸念されるため、安全な水質を保てるよう局所式よりも配慮が求められます。
局所式
局所式とは、給湯する個々の箇所で温水を作り供給する給湯方式です。小規模な建物で採用されるほか、大規模な建物であっても給湯箇所が分散し中央式では効率が悪い場合にも採用されます。
局所式では、一般に配管が短く済み、比較的コンパクトな設計ができます。ただし、給湯箇所が多い建物で局所式を採用すると、維持管理のコストが高くなりがちです。
給湯設備に関連する検査・清掃
給湯設備にはいくつか必要な検査・清掃があります。ビルで温水を安全かつ快適に提供するためには、適切な検査・清掃が欠かせません。ここからは給湯設備に関連する主な検査・清掃を解説します。
水質検査
中央式の給湯設備では、温水の汚染がより懸念されるため、給湯栓での水質検査が必要です。ただし、以下の条件を満たせば、水質検査のうち遊離残留塩素の含有率についての水質検査は省略してもよいことになっています。
- 給湯設備の維持管理が適切に行われていること
- 末端の給湯栓で温水の温度が55度以上に保持されていること
温水の汚染リスクが比較的低い局所式給湯設備では、温水の水質検査実施について規定がありませんが、だからといって温水の水質を安全な状態に維持しなくてよいわけではありません。
そもそも特定建築物で給水を適切に管理し、水質検査を行うことは、ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)で定められています。また、特定建築物にあてはまらない建物であっても、多くの人が利用する建物では、適切な維持管理の努力義務があります。
そして、給湯設備によって供給される温水に関しても、人が飲用や浴用など生活用に使う温水なのであれば、水道水質基準に適合する温水しなければなりません。
温水に関して特に懸念されているのは、レジオネラ属菌などによる健康への影響です。レジオネラ属菌は、一般に20度から50度ほどの環境で繁殖しやすい菌で、湯温の低い温水がたまっていると繁殖のリスクが高まります。
レジオネラ属菌の繁殖を防ぐため、貯湯タンク内の湯温を60度以上、末端の給湯栓でも55度以上に保つなど温度管理が大切です。とはいえ、高温の温水による火傷を防ぐことも重要であり、細やかな管理が必要となります。
ビル管理法やレジオネラ属菌については下記の記事をご参照ください。
ビル管法とは?対象となる特定建築物や建築物環境衛生管理基準を解説
貯湯タンク・配管など給湯設備の清掃
温水の水質を安全な状態に維持するため、水質検査をするだけでなく、給湯タンクをはじめとする給湯設備を点検・清掃し、適切に管理することが必要です。
給湯設備の清掃頻度については、厚生労働省の「建築物における維持管理マニュアル」で以下の内容が記載されています。
| 給湯設備の部位 | 清掃回数・方法 |
|---|---|
| 貯湯槽・膨張水槽 | 厚生労働省告示に基づく貯水槽の清掃を準用して行う。基本的に清掃頻度は1年に 1 回以上とするが、開放式の貯湯槽および開放式の膨張水槽であって、冷却塔が接近している場合など外部からの汚染の可能性が考えられる場合には、必要に応じて清掃回数を多くする。 |
| 給湯配管類 | 1年に1回以上厚生労働省告示に基づく給水系統配管の管洗浄に準じて管洗浄を行うことが望ましい。 |
| シャワーヘッド や水栓のコマ部 | 6ヶ月に 1 回以上定期的に点検し、1 年に 1回以上分解・清掃を実施する。 |
| その他、病院や高齢者対象の施設におけるシャワーヘッド | 1ヶ月に 1 回以上定期的に 70℃程度に昇温してフラッシングを実施する。 |
レジオネラ属菌を除去するためには、貯湯タンクだけでなく、配管などを含む給湯設備全体の清掃が必要です。また、特に多くの中央式給湯設備では、温水の加熱と貯留を繰り返しているため、通常の給水設備よりも徹底した清掃が必要だとされています。
給湯設備のメンテナンス・更新
給湯設備には耐用年数があり、いずれ更新が必要となります。しかし、個々の設備の寿命は、使い方や環境などによっても変動するため、必ずしもメーカーなどが公開している耐用年数とは一致しません。
現在ビルで使用している給湯設備の状態を把握し、実情に即した設備の更新計画を立てるためにも、定期的な点検・メンテナンスをおすすめします。
給湯設備に不具合や故障が発生してから対応しようとすると、利用者の安全や快適さも損ねるうえに、適切な対応をするだけの時間的余裕も持てません。給湯設備が問題なく使えるうちから、定期的な点検・メンテナンスをご検討ください。
なお、近年の給湯設備には省エネ性能の高いものも登場しています。既存の給湯設備を省エネ性能の高い給湯設備に入れ替えると、ビルのエネルギー効率が向上し、電気代やガス代などのランニングコストを抑えられる可能性があります。
給湯器の修理や交換については下記の記事をご参照ください。
ビルや施設の給湯器を修理するには?依頼先や症状別の対処法を解説
当社の強み・メリット
総合ビルメンテナンス企業である当社は、今回ご紹介した給湯設備にも携わっており、様々なビルにまつわるメンテナンス業務を一手に引き受けることができます。その他、当社には以下のような強みがありますので、ビルメンテナンスに関して何かご相談がありましたら、コニックスに是非ご相談ください。
コニックスへの問い合わせ
- 総合ビルメンテナンス企業として、建物にまつわる悩みごとはトータルでご相談をお受けすることができ、解決が可能です。
- 施設管理のベストパートナーであり続けられるよう、変化を恐れずチャレンジする文化(マインド)が根付いているため、より良いサービスを提供することができます。
- 創業(1955年)以来、長きに渡り培ってきた圧倒的な経験値(ノウハウ・スキル)を持ち、多種多様な顧客や施設利用者様から高い評価を得ています。
- エコチューニング事業所認定・エコチューニング技術者がいるため、省エネ知識も豊富で、水道光熱費といったランニングコストの軽減にも貢献できます。
- 特に愛知県においては拠点数が多く、何かあったときにすぐに駆け付けるといった充実した支援体制が整っています。