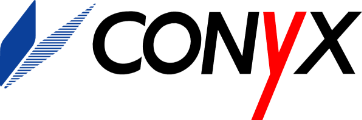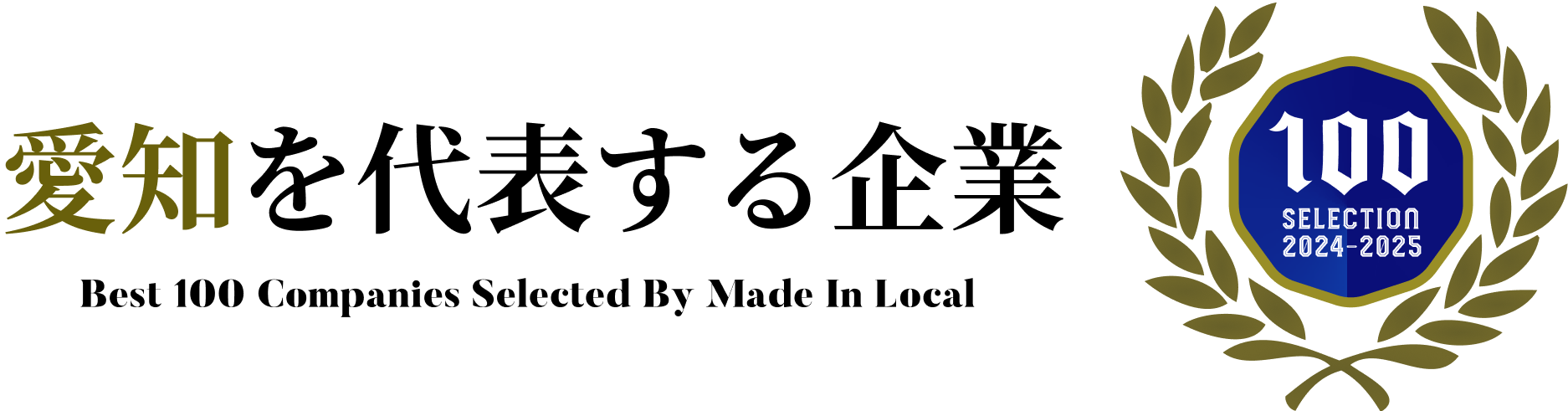ビルメンテナンス
ビルの落雷対策とは?避雷針を中心に近年の対策を解説

落雷リスクの増加が指摘されている昨今、改めてビルの落雷対策を検討したいビル管理者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、避雷針を中心に、近年の動向を踏まえながらビルの落雷対策をご紹介します。
高さ20m以上のビルでは基本的に避雷設備の設置は義務
建築基準法では、避雷設備について下記のように定められています。
高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
すなわち、高さ20mを超えるビル・建物には、基本的に避雷針などの避雷設備の設置が義務づけられています。
ビルの周囲に、所有者が同じで、より高いビルがあり、高い方のビルに雷が誘導されることが想定されるなどの特殊なケースを除いて、きちんと避雷設備を設置しなければなりません。
また、高さ20m未満のビルであっても、落雷リスクはあります。特に落雷リスクの高い地域や環境では、低層のビルであっても避雷設備の設置がおすすめです。
近年は、後述する誘導雷や逆流雷による雷サージ(一時的な過電圧・過電流)のリスクも認識され、避雷針ではない落雷対策にも注目が集まっています。
ビルに直撃する雷でなくても、ビル内部に被害を発生させることは少なくありません。落雷の影響からビルを守るために、避雷針を設置しない低層のビルであってもSPD(避雷器)の導入など何らかの落雷対策をおすすめします。
落雷が発生するとビルにどんな影響がある?

ビルに直撃するかたちであれ、周囲に落ちるかたちであれ、落雷が発生するとさまざまな影響が生じる可能性があります。ここからは、一般的なビルで想定される落雷の影響を解説します。
設備・機器の故障や誤作動
落雷が発生すると、ビル内にある設備・機器が故障や誤作動を起こす可能性があります。雷による一時的な過電圧・過電流が、設備・機器内部の部品を損傷させたり誤作動させたりすることもあるからです。
具体的には落雷によって以下のようなトラブルが発生することがあります。
- 受変電設備の誤作動・故障による停電
- ビル内の電子機器の故障・機器内部のデータ消失
- 空調設備・照明設備などさまざまな設備の故障
近年は設備・機器の高度化やネットワーク化が進んでおり、落雷によって設備・機器に故障が発生するとビル経営への影響も少なくありません。
落雷によって発生したトラブルを早期解決するだけでなく、そもそもトラブルが発生しないようにするための取り組みが必要です。
設備・機器の故障・誤作動は、ビルに雷が直撃してもしなくても、雷サージの侵入によって発生する可能性があります。ビルの設備・機器を雷からなるべく守るために、SPD(避雷器)の導入など、避雷針の設置以外の対策も大切です。
建物の破損
ビルに雷が直撃した場合は、建物が破損する可能性もあります。実際、かつて国会議事堂でも雷の直撃によって外壁の一部が落下する事故が発生しました。また、落雷や建物の状況によっては、火災が発生する場合もあります。
高層ビルでは、避雷針のみで雷の直撃を防ぎきれず、ビルの側面に雷が落ちる事例も発生しているため、ビルの側面に関しても落雷対策を進めている企業があります。
ビルの建物自体を守るためにも、落雷対策は必要です。
ビルに直撃しない雷の影響

ビルの落雷対策では、近年ビルに直撃しない雷による影響も注目されています。ビルに雷が直撃しなくても、周囲に落ちるだけで一時的な過電圧・過電流(雷サージ)が電力線や通信線を通じてビル内に侵入することがあるからです。
むしろ、雷被害のほとんどは、直撃雷ではない雷が原因であるとされています。そのため、ビルの落雷対策では、直撃雷ではない雷への対策も重要です。
参考:公共施設のための雷害対策ガイドブック|一般財団法人全国自治協会
ここからは、直撃雷ではない雷として、「誘導雷」と「逆流雷」の仕組みや影響を解説します。
誘導雷
誘導雷とは、付近に落雷することによって、強い電磁界が生まれ、電磁誘導により付近の電力線や通信線などに雷サージが発生して、電力線や通信線を通じて建物内にも過電圧・過電流が浸入する現象を指します。
過電圧・過電流が起きた先に設備・機器があると、内部の部品を損傷させるなどして故障につながる可能性があります。誘導雷の主な対策はSPDの導入などです。
逆流雷
逆流雷とは、建物や大地に雷が落ちた後に、雷サージが接地(アース)から逆流し、電力線や通信線などに流れ込む現象です。逆流雷の場合も、ビル内にある過電圧・過電流によって設備・機器の故障や誤作動を招くため、SPDの設置など相応の対策が必要です。
ビルの落雷対策
ビルの落雷対策として、具体的に何をすればよいのか気になる方もいるでしょう。ここからは、ビルで行われている主な落雷対策をご紹介します。
避雷針の設置
一般的な落雷対策は、避雷針の設置です。前述の通り、高さ20mを超えるビルでは基本的に避雷設備の設置が義務づけられており、避雷針が避雷設備として採用されています。
従来型の避雷針であれば、避雷針が雷をある程度誘導し、周囲の構造物の代わりに雷を受けてから地面などに逃がすことによって、落雷の被害軽減が期待できます。
しかし、実際に避雷針で雷を受けてしまうと、雷の規模によっては被害なしでは済みません。また、そのほかの落雷対策が十分に行われていないと、電流を避雷針から地面などに逃がす過程で、鉄骨に沿わせた他の設備の配線などに影響が生じる場合もあります。
そのため、近年では雷が落ちにくくなる新しいタイプの避雷針に注目が集まっています。
ビル側面への受雷部設置
ビルの高さによっては、ビルの側面に落ちる雷の対策も必要です。ビルが雷雲よりも高いと、ビルの横から雷が発生するからです。
避雷針が役割を果たせる角度や範囲は決まっており、避雷針がカバーできない角度で落雷が発生すると、うまく雷を誘導できずビルを守れません。
そのため、ビル側面への落雷が想定される高層ビルでは、側面でも雷を受けて逃がせるように金属製の受電部を設置している例もあります。
SPD(避雷器)
ビルの中の設備・機器を守るために、SPD(避雷器:Surge protective device)にも注目が集まっています。
SPDを導入すると、避雷針では防げない誘導雷などによる雷サージの影響からも設備・機器を守りやすくなります。
SPDによって、設備や機器にかかる過電圧を抑制し、設備・機器の故障・誤作動を防げるからです。
周囲の環境や建物の高さによって避雷針の設置を必要としないビルであっても、ビル内部の設備・機器を雷サージから守る必要はあるため、落雷対策の一つとしてSPDの導入はおすすめです。
避雷針のメンテナンス
避雷針の耐用年数は15年ほどとされています。しかし、個々の避雷針の寿命は、使用状況や設置環境によっても変動するため、定期的に点検・メンテナンスをして避雷針の状態を確認しましょう。
点検・メンテナンスの目安は1年に1度です。定期的な点検・メンテナンスをせずに、避雷針の導線劣化などを放置していた場合、落雷被害を軽減するという避雷針の役割が果たせなくなる可能性があります。
避雷針をはじめ、避雷設備を適切にメンテナンスし、落雷の被害を抑えましょう。
当社の強み・メリット
総合ビルメンテナンス企業である当社は、様々なビルにまつわるメンテナンス業務を一手に引き受けることができます。当社には以下のような強みがありますので、この記事でご紹介した落雷対策など、ビルメンテナンスに関して何かご相談がありましたら、コニックスに是非ご相談ください。
コニックスへの問い合わせ
- 総合ビルメンテナンス企業として、建物にまつわる悩みごとはトータルでご相談をお受けすることができ、解決が可能です。
- 施設管理のベストパートナーであり続けられるよう、変化を恐れずチャレンジする文化(マインド)が根付いているため、より良いサービスを提供することができます。
- 創業(1955年)以来、長きに渡り培ってきた圧倒的な経験値(ノウハウ・スキル)を持ち、多種多様な顧客や施設利用者様から高い評価を得ています。
- エコチューニング事業所認定・エコチューニング技術者がいるため、省エネ知識も豊富で、水道光熱費といったランニングコストの軽減にも貢献できます。
- 特に愛知県においては拠点数が多く、何かあったときにすぐに駆け付けるといった充実した支援体制が整っています。