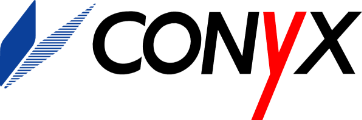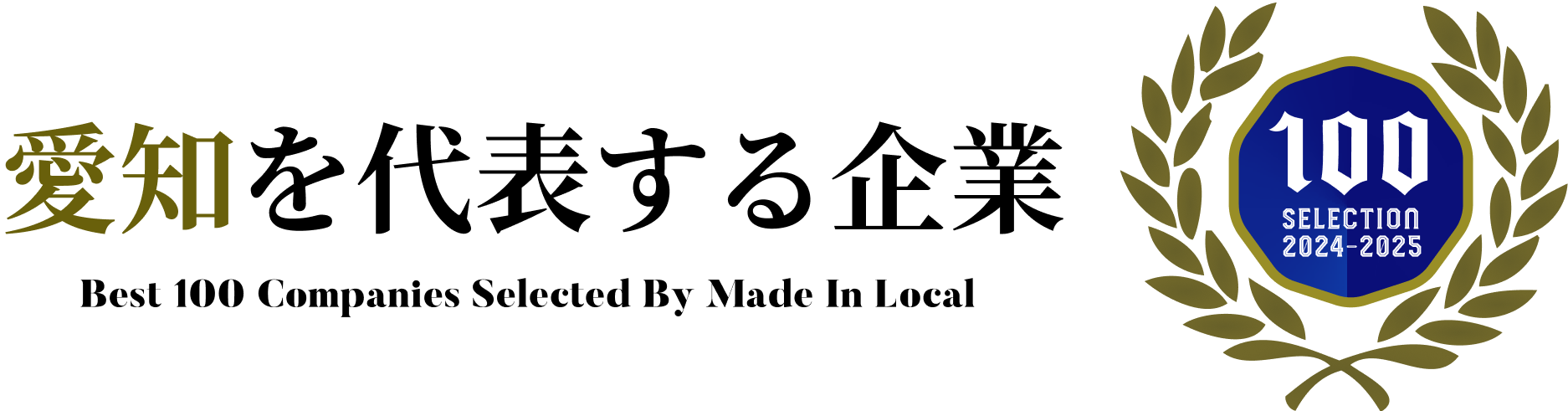修理
ビルの防水工事:工法の種類や工事の必要性・タイミングを解説

ビルの寿命を長く保つために、しっかりと防水工事を行っておきたいと考える管理者の方は多いのではないでしょうか。ビルの防水工事に関して基本的な知識を得ておけば、スムーズに納得しながら工事を依頼しやすくなります。
この記事では、ビルの防水工事に関して、工事の必要性やタイミング、種類など基本的な事柄を解説します。
ビルの防水工事とは
ビルの防水工事とは、ビルの建物が雨水などによって劣化しないよう、建物内部への水の侵入を防ぐための工事です。ビルでは主に以下の場所に防水工事を施します。
- 屋上・屋根
- 外壁
- ベランダ・バルコニー
- 廊下
ビルは、ほとんど勾配がないか水平な屋根である「陸屋根」を採用している建物が多く、水はけが悪くなりやすいため、防水工事を適切に行うことが大切です。
また、陸屋根でない屋根や建物の他の部分であっても、長く放置すると地震や台風による細かな揺れや紫外線などの影響で劣化が進み、防水機能が低下します。
ビルの防水機能を維持し、建物の劣化を防ぐためには定期的な防水工事が必要です。
ビルの防水工事が必要な理由

ビルの防水工事にはまとまった費用が必要になるため、なかなか準備を進められない管理者の方もいるかもしれません。しかし、将来の修繕コストを抑え、ビルの資産価値を維持するために、防水工事は欠かせません。
ここからは、防水工事の必要性について簡単に解説します。
建物の劣化を防ぐため
防水工事は建物の劣化を防ぐために必要です。経年劣化などにより、ビルの防水機能が失われると、雨水などが建物の躯体(壁や柱などの構造体)にまで浸み込んでしまいます。
結果、躯体の劣化を早め、ビル自体の寿命を大きく縮める可能性があります。劣化した躯体の修繕を行うのは簡単ではなく、費用も高額です。
たしかに、防水工事には費用がかかりますが、将来の修繕費用を抑えやすくなることを考慮すれば、必要性の高い出費です。
雨漏りを防ぐため
建物の劣化を防ぐことに付随して、雨漏りを防ぐためにも適切な防水工事は大切です。雨漏りが発生すると、室内の環境や見た目が悪くなるのはもちろん、入居状況によってはテナントの活動にも支障が出ます。
雨漏りによってパソコンなどの機器や商品、書類といったテナントの財産を汚損する可能性も考えられるでしょう。また、雨漏りが発生する状況では、躯体にも水が浸み込んでいるため、建物の劣化も進んでいます。
雨漏りが発生した後では、対処や修繕に多くの費用と労力がかかります。雨漏りを未然に防げるよう、定期的に防水工事を行いましょう。
カビを防ぐため
防水機能が低下し、建物内部にまで水が浸入する状況では、カビも発生しやすくなります。カビが発生すると、見た目が悪いだけでなく、アレルギー反応や呼吸器症状などのかたちでビルの利用者の健康に悪影響を及ぼす可能性もあります。
また、カビ自体が建物の劣化を招くため、建物の耐久性の面でも看過できません。なるべくカビを発生させないよう、ビルの防水機能を維持しましょう。
防水工事の工法の種類

ビルの防水工事にはさまざまな工法があります。すべての工法を紹介することはできませんが、屋上などに用いられやすい工法を中心に、防水工事の主な工法をご紹介します。
アスファルト防水工法
アスファルト防水工法は、古くから採用されている人気の工法です。アスファルトを用いて、屋上などに防水性を持たせます。作業内容や使用するアスファルトによって、以下のようにさらに細かく工法が分かれます。
- 熱工法
- 常温工法
- トーチ工法
アスファルト防水工法はコストに対して防水効果が高く、耐久性にも優れています。しかし、アスファルトにはそれなりの重量があり、工事中に独特のニオイが発生するため、ビルの使用状況や施工場所によっては適しません。
ウレタン防水工法
ウレタン防水工法は、ウレタン樹脂を塗布する工法です。ウレタンは軽量で防水性能が高く、下地が多少平坦でなくても施工できるため人気です。
施工コストも比較的低く、古い防水塗膜の上からでも施工しやすいメリットがあります。しかし、きちんと防水性能を持たせつつ施工するためには、高い技術が必要です。
シート防水工法
シート防水工法は、塩化ビニルや合成ゴムでできたシートを貼り付ける工法です。すでにできあがったシートを工事に使用するため、工期が比較的短く済むメリットがあります。
塩ビシート・ゴムシートともに伸縮性があるため、多少の揺れでは断裂しにくいのも特長です。塩ビシートはデザイン性の高い製品もあり、屋上などに防水性を持たせながらおしゃれな外観にすることもできます。
しかし、いずれのシートも平坦な下地でなければ採用が難しいデメリットがあります。また、シートに継ぎ目が発生するため、接着剤の性能によって防水性能が左右されやすい面もあります。
FRP防水工法
FRP防水工法は、ガラス繊維とプラスチックが組み合わさった繊維強化プラスチック(Fiberglass Reinforced Plastics:FRP)を使用する工法です。船や浴槽に使われることもある信頼性の高い工法で、軽量と高耐久を実現できます。
軽量さを活かして、ベランダ・バルコニーへの施工にも採用されます。また、対候性に優れているのも大きな魅力です。
しかし、ややコストが高いことと、伸縮性に乏しく揺れに弱いことがデメリットです。地震や台風などで建物が揺れた際には、割れが発生する場合もあるため、こまめなメンテナンスを必要とします。
防水工事を行うタイミング
防水工事をいつ頃行うべきか悩む方もいるかもしれません。防水工事のタイミングは防水層の耐用年数を参考にしつつ、建物の状況に応じて判断するのがおすすめです。
ここからは、防水工事を行った方がよいタイミングをご紹介します。
点検で異状が発見された時
屋上や外壁などの点検で、ビルの防水機能に影響する異状が発見された場合は、なるべく早く防水工事を行うなどして対処しましょう。
ビルの屋上や外壁であれば、定期的な点検・調査を行っていることが多いはずです。例えば、いわゆる12条点検の対象となる建物であれば、屋上や外壁の点検・調査も義務づけられています。
点検などで発見された異状を放置すると、建物の劣化が進み、修繕費が高くつくことになりかねません。定期的に点検を行い、必要に応じて防水工事を依頼しましょう。
屋上や外壁の点検・調査に関しては下記の記事もご参照ください。
劣化や異状に気付いた時
点検のタイミングではなくても、劣化や異状に気付いた場合は業者に相談し、なるべく早く対応を検討しましょう。普段から気付きやすいのは、屋上や外壁などの表面に施された塗装である「トップコート」の劣化です。
トップコートが劣化すると、トップコートの下にある防水層を十分に保護できなくなるため、防水機能が低下している可能性があります。
トップコートの劣化を示すサインとして、よく見つかるのは以下の症状です。
- 塗装の色あせ
- ひび割れ
- チョーキング(塗装を触ると粉がつく)
- 膨らみ
塗装などの劣化や異状に気付いた際には、業者に相談するようにしましょう。
外壁補修・塗装に関しては下記の記事もご参照ください。
前回の施工から10~12年ほどが経過した時
防水工事を含め、ビルの修繕工事は10~12年ほどに1度を目安に行うのが一般的です。適切なタイミングで修繕工事を行うことで、ビルの安全性や耐久性をなるべく維持します。
とはいえ、屋上や外壁などの防水機能がどのくらい続くかは、選択した工法や施工状況、ビルの環境によっても異なります。
10~12年に1度というのは、あくまで目安として参考にしつつ、定期的な点検によって実際に工事が必要になる時期を見積もりましょう。
修繕工事に関しては下記の記事もご参照ください。
当社の強み・メリット
総合ビルメンテナンス企業である当社は、様々なビルにまつわるメンテナンス業務を一手に引き受けることができます。当社には以下のような強みがありますので、この記事でご紹介した防水工事など、ビルメンテナンスに関して何かご相談がありましたら、コニックスに是非ご相談ください。
コニックスへの問い合わせ
- 総合ビルメンテナンス企業として、建物にまつわる悩みごとはトータルでご相談をお受けすることができ、解決が可能です。
- 施設管理のベストパートナーであり続けられるよう、変化を恐れずチャレンジする文化(マインド)が根付いているため、より良いサービスを提供することができます。
- 創業(1955年)以来、長きに渡り培ってきた圧倒的な経験値(ノウハウ・スキル)を持ち、多種多様な顧客や施設利用者様から高い評価を得ています。
- エコチューニング事業所認定・エコチューニング技術者がいるため、省エネ知識も豊富で、水道光熱費といったランニングコストの軽減にも貢献できます。
- 特に愛知県においては拠点数が多く、何かあったときにすぐに駆け付けるといった充実した支援体制が整っています。